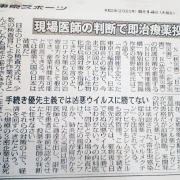浪漫の歌⑵
「みだれ髪」と星野哲郎さん
令和二年五月二十三日 (No.1938)
濱野成秋
女は断崖から身を投げるか
どん底になれば誰だって歌が出る。星野さんも僕も。
引かれ者の小唄でなくとも、人生詠嘆の果てに唇から歌がこぼれる。
この歌もそれだ、どん底で出来たから俺の心に憑りついてゐ続ける。
ここに女が一人、断崖絶壁の岬に向かう。吹き付ける風にみだれる髪。か細い指にからまる長い鬢のほつれ。裾が肌けて覗ける白い脚。それを気にも留めず、女は絶壁に向け一歩、一歩。死ぬ気だ、これは。
この思い詰めを詩にした男がゐる。星野哲郎である。彼は若くない。もう失恋する年でも身投げする年でもない。都会に戻れば著作権協会の理事長だ。自分でも電話をとる身なのに人には言えぬ、手術した臓器が、今日も痛んで…と、電話だ。俺からの電話をとる。身体が苦しんでいるから声もかすれる。大丈夫ですか? あ、はい。お忙しい? いいえ、いらっしゃいよ、またお会いしたいから。
ひばりちゃん復帰第一作がこの名作「みだれ髪」。船村徹のイントロが俺の胸で疼きだす。僕は言葉に詰まって、じゃあ三時に。はいお待ちします。俺も彼も著作権の話はしなくなった。が自然と会いたくなる。
この老人は現代まれに見る確かな腕のもちぬし。新語作りの名人。職人技と鋭利な感覚を兼ね備えたプロフェッショナル。その星野の心の奥底からいまだ消えない女性が見え隠れして、俺は事務所に向かう。
「みだれ髪」と星野哲郎さん
令和二年五月二十三日 (No.1938)
濱野成秋
女は断崖から身を投げるか
どん底になれば誰だって歌が出る。星野さんも僕も。
引かれ者の小唄でなくとも、人生詠嘆の果てに唇から歌がこぼれる。
この歌もそれだ、どん底で出来たから俺の心に憑りついてゐ続ける。
ここに女が一人、断崖絶壁の岬に向かう。吹き付ける風にみだれる髪。か細い指にからまる長い鬢のほつれ。裾が肌けて覗ける白い脚。それを気にも留めず、女は絶壁に向け一歩、一歩。死ぬ気だ、これは。
この思い詰めを詩にした男がゐる。星野哲郎である。彼は若くない。もう失恋する年でも身投げする年でもない。都会に戻れば著作権協会の理事長だ。自分でも電話をとる身なのに人には言えぬ、手術した臓器が、今日も痛んで…と、電話だ。俺からの電話をとる。身体が苦しんでいるから声もかすれる。大丈夫ですか? あ、はい。お忙しい? いいえ、いらっしゃいよ、またお会いしたいから。
ひばりちゃん復帰第一作がこの名作「みだれ髪」。船村徹のイントロが俺の胸で疼きだす。僕は言葉に詰まって、じゃあ三時に。はいお待ちします。俺も彼も著作権の話はしなくなった。が自然と会いたくなる。
この老人は現代まれに見る確かな腕のもちぬし。新語作りの名人。職人技と鋭利な感覚を兼ね備えたプロフェッショナル。その星野の心の奥底からいまだ消えない女性が見え隠れして、俺は事務所に向かう。
1.
髪のみだれに 手をやれば
赤い蹴出しが 風に舞う
憎や恋しや塩谷の岬
投げて届かぬ 想いの糸が
胸にからんで 涙をしぼる
協会事務所はせまっ苦しいけど、二人で出たらのびのび。蹴出しって言葉、ないんですけれど…つまずき歩きをしながら本人が笑う。
作ったと言われてもいいじゃないですか。心の琴線が糸になるし、片思いが片情けに。だから心にまといつく。出だしは岩田仙太郎の女だ、幽玄で思い詰めて…後半、思いの糸となるから、引きずり込まれる。こっくり頷く星野…船村さん、三味線口調の琴線でうまいね。幽玄か、なるほど。
星野さん、これって、死にに行く歌だな、とみんなが思うから、船村さんのイントロが始まると聴く方も構える。自分も女の裏人生が分かる気がして。ひばりちゃんの哀しい一人酒に通じるけど…あ、そういえばあれからどうしました、あの女性は? …と訊きたいところだが、
「周防大島の小学校の同級生の子は…」とも訊けず、「周防大島って、明治にたくさん移民で渡米したから、がらんとした家並があって…」と切り出すと、「ええ、移民するか漁師になるか志願するか…」
志願? ああ兵隊ね…でも星野さんは戦中派でも戦後は漁師が男らしくなりたかったとか…本気で漁師になりたかった?
髪のみだれに 手をやれば
赤い蹴出しが 風に舞う
憎や恋しや塩谷の岬
投げて届かぬ 想いの糸が
胸にからんで 涙をしぼる
協会事務所はせまっ苦しいけど、二人で出たらのびのび。蹴出しって言葉、ないんですけれど…つまずき歩きをしながら本人が笑う。
作ったと言われてもいいじゃないですか。心の琴線が糸になるし、片思いが片情けに。だから心にまといつく。出だしは岩田仙太郎の女だ、幽玄で思い詰めて…後半、思いの糸となるから、引きずり込まれる。こっくり頷く星野…船村さん、三味線口調の琴線でうまいね。幽玄か、なるほど。
星野さん、これって、死にに行く歌だな、とみんなが思うから、船村さんのイントロが始まると聴く方も構える。自分も女の裏人生が分かる気がして。ひばりちゃんの哀しい一人酒に通じるけど…あ、そういえばあれからどうしました、あの女性は? …と訊きたいところだが、
「周防大島の小学校の同級生の子は…」とも訊けず、「周防大島って、明治にたくさん移民で渡米したから、がらんとした家並があって…」と切り出すと、「ええ、移民するか漁師になるか志願するか…」
志願? ああ兵隊ね…でも星野さんは戦中派でも戦後は漁師が男らしくなりたかったとか…本気で漁師になりたかった?
頷かない。ぼそりぼそり歩いてプレドールの階段で、濱野さんも身体が弱かったって…海には向かんよね、せんせもわたしも…
ええ…それより、あの女性との再会は?
同じいわき市でも塩屋崎じゃなかった…駅前の何とか…。
コーヒーを啜る。
「私のこと、哲っちゃんって呼ぶわけ、その子。勉強家で、いや僕じゃなく、その子、ご大家の子で、ノートづくり、立派だった。でも家が零落されて、もう網元の家も何もかも…」と首を振る。
あ、だから糸さんは酒場に出た…それも大島からうんと離れたいわきで」
こっくりうなずく老人はコーヒーを啜る。伏し目で、その女性、今なにしてるか、言いたそうでおっしゃらない。訊かぬが花だ。
2.
捨てたお方の しあわせを
祈る女の 性かなし
辛や 重たや わが恋ながら
沖の瀬をゆく 底引き網の
舟に乗せたい この片情け
ええ…それより、あの女性との再会は?
同じいわき市でも塩屋崎じゃなかった…駅前の何とか…。
コーヒーを啜る。
「私のこと、哲っちゃんって呼ぶわけ、その子。勉強家で、いや僕じゃなく、その子、ご大家の子で、ノートづくり、立派だった。でも家が零落されて、もう網元の家も何もかも…」と首を振る。
あ、だから糸さんは酒場に出た…それも大島からうんと離れたいわきで」
こっくりうなずく老人はコーヒーを啜る。伏し目で、その女性、今なにしてるか、言いたそうでおっしゃらない。訊かぬが花だ。
2.
捨てたお方の しあわせを
祈る女の 性かなし
辛や 重たや わが恋ながら
沖の瀬をゆく 底引き網の
舟に乗せたい この片情け
私がも少し気も強く腕っぷしも強かったら、そこの家の養子になっていたかも…底引き網の船を…そう10隻はあったかな。それに乗って…
あ、だから、岬から身を投げたらいったん底に沈んで網に掛かり…
いや、そんなの私の想像ですよ、糸ちゃんはもっとしっかりしていて。運動会の片づけのとき、てっちゃんもっとしっかりしてって、涙をためて忠告してくれました…でも僕は船に乗りたいけど…同級生でそばで聞いていた子らが黒板にでかでか、哲郎、糸の名前並べて相合傘にしよった。もう大島にはおれなくなりました。
それで、糸さんは、自分は捨てられたのだと、思われたのかな…
捨てたんではない、僕のように心も体も虚弱では、みんなと肩並べてやれる場所がない…僕なんか…半病人で役立たずで…
3.
春は二重に 巻いた帯
三重に巻いても 余る秋
暗や 果てなや 塩谷の岬
見えぬ心を 照らしておくれ
ひとりぼっちに しないでおくれ
あ、だから、岬から身を投げたらいったん底に沈んで網に掛かり…
いや、そんなの私の想像ですよ、糸ちゃんはもっとしっかりしていて。運動会の片づけのとき、てっちゃんもっとしっかりしてって、涙をためて忠告してくれました…でも僕は船に乗りたいけど…同級生でそばで聞いていた子らが黒板にでかでか、哲郎、糸の名前並べて相合傘にしよった。もう大島にはおれなくなりました。
それで、糸さんは、自分は捨てられたのだと、思われたのかな…
捨てたんではない、僕のように心も体も虚弱では、みんなと肩並べてやれる場所がない…僕なんか…半病人で役立たずで…
3.
春は二重に 巻いた帯
三重に巻いても 余る秋
暗や 果てなや 塩谷の岬
見えぬ心を 照らしておくれ
ひとりぼっちに しないでおくれ
二重にとか三重とかいうと、半幅帯か。玄人だから下目に結んで。着物は黄八丈か大島ね。ひらめく蹴出しは長襦袢の裏地で玄人好みのお色気たっぷりの桃色紅…と僕。
濱野さんだとそこまで読んじゃいますか、と笑う。…糸さんは小学生のころからマドンナ的存在でね。僕が一番よく覚えてる子だった。
「とにかく大人になってから再会した。もう自由やないですか、結婚は難しくとも何度も会える…あ、失礼、そんな乱暴な人生はだめか…」と俺。
首を横に振り、僕も出来れば時々は会いたかった…でもね、次に会ったとき、とんでもなく窶(やつ)れてて、糸ちゃん…目のくりっとした丸顔の明るい子だったのに、頬がこけて面長になっていて、鬢のほつれに指をやる、その反り返った小指で目を抑え、この目、時々見えんのよ、ひとり暮しだから誰にも迷惑かけないけれど…ああ、嘆いてなんかいないわ、ひとりぼっちでいいのよ、私をこのままにしておいてね、てっちゃん…
星野さんはこの話、ひばりさんにしか話さなかったそうで、ひばりさんは心で受けとめ、舞台に立つとき涙をいっぱい浮かべて歌う。星野さんは著作権協会の事務所でそれを視る。
ひばりさんも逝き星野さんも逝き、糸さんももはやこの世の人ではないかもしれない。でも、「みだれ髪」の歌だけは今日もどこかのカラオケ酒場で生きている。詩的真実は永遠なり。この小文もまた然り。
(No.1938は以上)
濱野さんだとそこまで読んじゃいますか、と笑う。…糸さんは小学生のころからマドンナ的存在でね。僕が一番よく覚えてる子だった。
「とにかく大人になってから再会した。もう自由やないですか、結婚は難しくとも何度も会える…あ、失礼、そんな乱暴な人生はだめか…」と俺。
首を横に振り、僕も出来れば時々は会いたかった…でもね、次に会ったとき、とんでもなく窶(やつ)れてて、糸ちゃん…目のくりっとした丸顔の明るい子だったのに、頬がこけて面長になっていて、鬢のほつれに指をやる、その反り返った小指で目を抑え、この目、時々見えんのよ、ひとり暮しだから誰にも迷惑かけないけれど…ああ、嘆いてなんかいないわ、ひとりぼっちでいいのよ、私をこのままにしておいてね、てっちゃん…
星野さんはこの話、ひばりさんにしか話さなかったそうで、ひばりさんは心で受けとめ、舞台に立つとき涙をいっぱい浮かべて歌う。星野さんは著作権協会の事務所でそれを視る。
ひばりさんも逝き星野さんも逝き、糸さんももはやこの世の人ではないかもしれない。でも、「みだれ髪」の歌だけは今日もどこかのカラオケ酒場で生きている。詩的真実は永遠なり。この小文もまた然り。
(No.1938は以上)